おなじみの池上彰さんの今回の本のテーマは、「情報を活かす」。
構成をみると
序章 情報活用力をいかに高めるか
第1章 私の情報収集術
第2章 私の取材・インタビュー術
第3章 私の情報整理術
第4章 私の読書術
第5章 私のニュースの読み解き方
第6章 私の情報発信術
1 情報発信のためだけでなく、自分の考えを整理するために文章を書く
2 書いたものを発表してみよう
3 相手への想像力を働かせ、わかりやすい説明の工夫をしよう
となっていて、書籍・新聞・人といったリソースからの情報の集め方、そして情報の発信の方法といったことが内容で。情報の整理活用といった狭い範囲でないのが、本書のおトクなところであろう。
で、その一端は
メディアの人間や専門家という人種は「視聴者や聞き手は何がわからないか」がわからなくなっている(P24)
といった反省を踏まえながら
民放の夜のニュースは、大都市部のサラリーマンの視点で番組がつくられる(P42)
東京で読んでいる全国紙は東日本のブロック紙、九州で読んでいる全国紙は九州のブロク紙なのだと心得ておくべき(P47)
といったメディアの世界で長く活躍してきたらしい辛口コメントがでてくるのが興味深い。
さらには
自分に基礎知識のない分野で、これから注目を集めそうなテーマが出てきたときは必ず読書で下地をつくるようにしています。何冊かの本を読んで、そのジャンルの基礎的な知識を仕入れておくのです(P139)
何か本格的に知りたいテーマが出てきたとき、どうやって「参考になる本」を探せばいいのでしょうか。
私は、とりあえず大きな書店に行って、そのテーマに関連するジャンルの本をまとめて買ってきます。書店の店頭で、書名や装丁を一つひとつ見ていくことで、「このテーマでこんな本があるのか」と気づかされます。
このように本探しはもっぱらリアル書店です。なぜならネット書店の検索では、読むべき本にたどりつかないことが多いからです(P146)
(評論家の)立花(隆)さんも、本屋に行って、そのジャンルに関係するものを全部買い、課片っ端から読んでいくうちに、そのジャンルの基本となる一冊か二冊に行き当たるのだそうです。これが「定本」です。
定本とは、ほかの多くの本や雑誌が参考図書としているような、そのジャンルの基本図書のこと。ほとんどその定本をベースに書かれていて、最新事情や著者の意見をほんの少し加えただけ、という本も珍しくありません。したがって、この定本をしっかり読んでおけば、ほかの本にもおなじようなことが書いてあるので、簡単に目を通すだけですぐに把握できる、というのです(P147)
という未知の分野の知識・情報の取得方法や
プレゼンテーションの原稿を考えるときにも、最初に「とにかくすばらしいんです」とか、「とにかく驚くべきことなんです」と書いてしまいましょう。それから、「それは~だからです」と話を展開させていきます。
原稿が完成したら、「とにかく~」という文章を削除します。こうすれば、労せずしてプレゼンでいちばん伝えたいことを、最初に述べることができます(P237)
や
「起承転結」で大事なのは「起」でとりあげたテーマを、「結」で再び取り上げることです。
こういう構成にしておくと、最後まで読んだ読者は「ああ、そうか。これが冒頭の話だったのだ」と納得します「起」の部分のエピソードに必然性が生まれ、本全体のまとまりがよくなります。(P238)
といった「表現の技」的なことが披瀝されているので、新刊で買っても損はないだろう。
メディアの世界で長く活躍している人の様々な手法を、手っ取り早く知りたいのであれば、手軽な一冊でありましょうな、
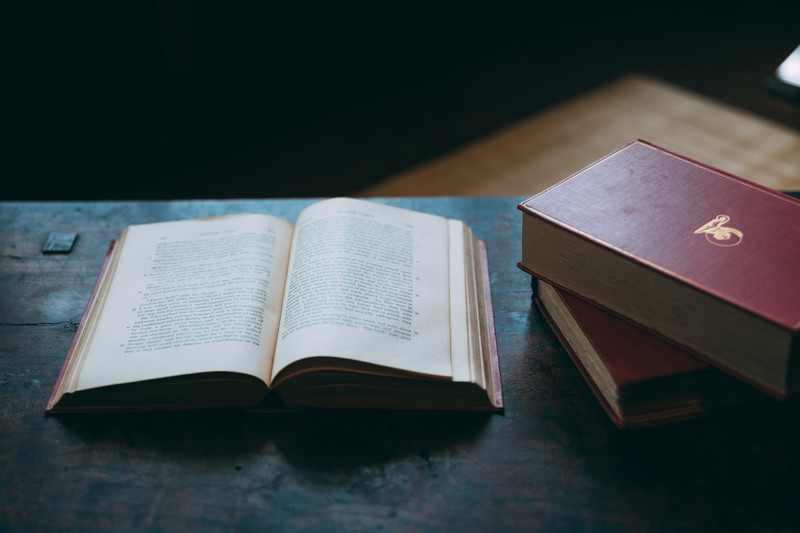

コメント