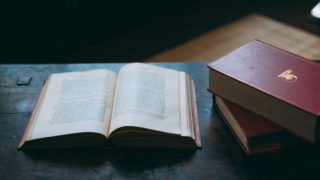 テクノロジー
テクノロジー テクノロジーを”キー”に未来を見通せー佐藤航陽「未来に先回りする思考法」
物事が大きく変化してから、「まさかこんな風になるなんて」と自分の先見性のなさや、先の見通しの甘さを後悔し人はいませんか。「未来」っていうのは、たいてい自分の思っているところと別のゴールに向けっていくか、横のほうにそれていくものです。 未来を...
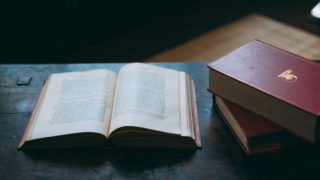 テクノロジー
テクノロジー 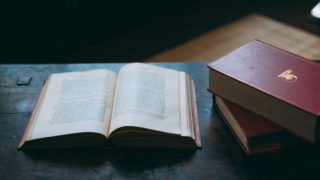 テクノロジー
テクノロジー 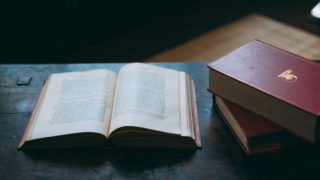 テクノロジー
テクノロジー 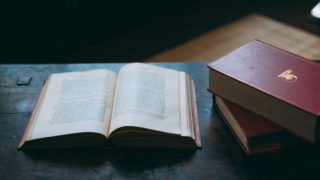 テクノロジー
テクノロジー 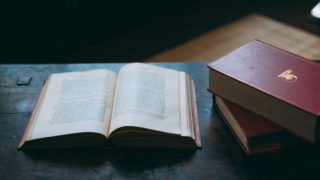 テクノロジー
テクノロジー 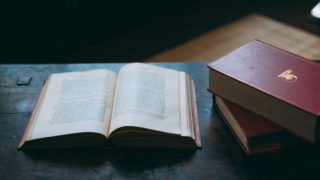 テクノロジー
テクノロジー 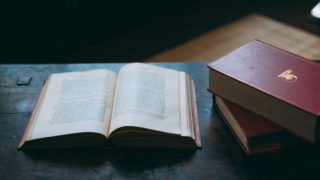 テクノロジー
テクノロジー 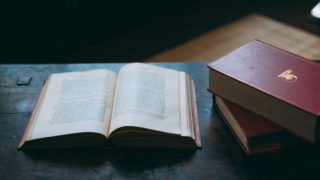 テクノロジー
テクノロジー 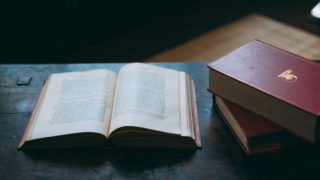 テクノロジー
テクノロジー