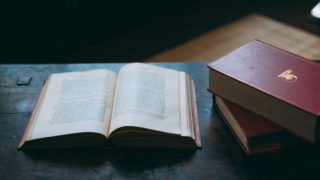 プランニング
プランニング ”売れるモノは何か”から、プランニングのヒントを考える ー 水野学「アウトプットのスイッチ」(朝日文庫)
商品企画、パッケージデザインなどなどブランドづくりについて幅広くコンサルティングをして活躍している、クリエイティブ・ディレクターの水野学氏が、 「『アウトプットの質』が、売れるか売れないかを決める」 と断言して、そのアウトプットの質をどうし...
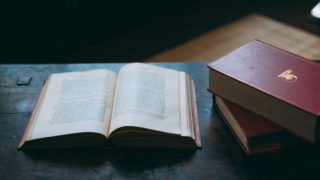 プランニング
プランニング 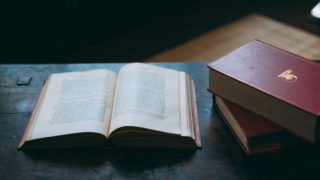 プランニング
プランニング 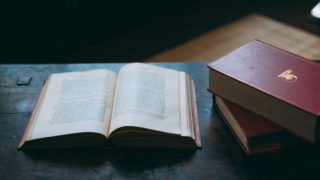 プランニング
プランニング 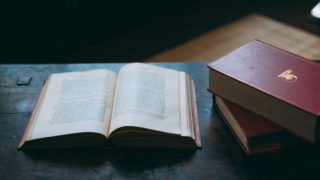 プランニング
プランニング 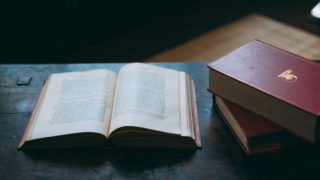 プランニング
プランニング 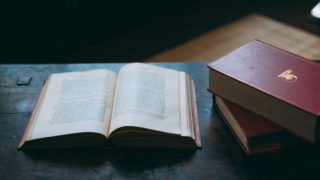 プランニング
プランニング