「日本史の謎は「地形」で解ける」の続編に当たるのが本書。前の本は、頼朝の鎌倉開府や家康の江戸開府、あるいは忠臣蔵の事件などが、人文的な事実だけで動いたわけではなく、根底に「地形」「地理」上のわけがあった、ということを見事に論じてみせ、爽快な目鱗を感じさせてくれた。
続編の「文明・文化編」は個別の歴史上のイベントだけでなく、国民性とかも含めてちょっと大きな事象が「地形」「地理」的な影響下にあることを論じてみせている。
構成は
第1章 なぜ日本は欧米列強の植民地にならなかったか①
地形と気象からの視点
第2章 なぜ日本は欧米列強の植民地にならなかったか②
「海の中」を走った日本初の鉄道
第3章 日本人の平均寿命をV字回復させたのは誰か
命の水道水と大正10年の謎
第4章 なぜ家康は「利根川」を東に曲げたか
もう一つの仮設
第5章 なぜ江戸は世界最大の都市になれたか①
「地方」が支えた発展
第6章 なぜ江戸は世界最大の都市になれたか②
エネルギーを喰う都市
第7章 なぜ江戸は世界最大の都市になれたか③
広重の「東海道五十三次」の謎
第8章 貧しい横浜村がなぜ、近代日本の表玄関になれたか
家康が用意した近代
第9章 「弥生時代」のない北海道でいかにして稲作が可能になったか
自由の大地が未来の日本を救う
第10章 上野の西郷隆盛像はなぜ「あの場所」に建てられたか
樺山資紀の思い
第11章 信長が天下統一目前までいけた本当の理由とは何か
弱者ゆえの創造性
第12章 「小型化」が日本人の得意技になったのはなぜか
「縮み志向」の謎
第13章 日本の将棋はなぜ「持駒」を使えるようになったか
地形が生んだ不思議なゲーム
第14章 なぜ日本の国旗は「太陽」の図柄になったか
気象が決める気性
第15章 なぜ日本人は「もったいない」と思うか
捨てる人々・捨てない人々
第16章 日本文明は生き残れるか
グラハム・ベルの予言
第17章 【番外編】ピラミッドはなぜ建設されたか①
ナイル川の堤防
第18章 【番外編】ピラミッドはなぜ建設されたか②
ギザの3基の巨大ピラミッドの謎
で、辺境に住まう身にとって嬉しかったのは「なぜ江戸は世界最大の都市になれたか」のあたりで
江戸の都市インフラは、地方の大名たちの財力で次々と整備されていった。ここで、地方大名たちの財力とは、領民から集めた年貢であったことは言うまでもない。つまり、江戸の都市インフラは、全国の地方の人々の年貢で整備されていったのだ。(中略)下部構造の上に花開いた江戸の上部構造の商業、文化、芸術の繁栄も、地方の人々に依存していた。・・それは「参勤交代」であった。・・江戸中期になると、ほとんどの大名は江戸生まれになっていった。こうなると妻子が江戸の人質というより、大名が地方の領地へ単身赴任するという構図になる。(P99)
とか
江戸時代、消費生活を支えたのは地方の大名たちであった。彼らの消費は江戸の経済と文化の繁栄の源であった。現在も多くの地方の人々が東京で消費し、東京の経済と文化を支えている。その消費を端的にあらわしているのが東京の「学生」である(P104)
とか「地方部のことも考えてくれる東京人がいたのか」と思う反面、東京(江戸)への集中構造が江戸時代から綿々とシステム的に続いていると思うと、今流行りの「地方創生」もどうなることか・・といらぬ心配をしてしまう。
もひとつ印象深いのは、信長の話。
信長の本拠地の清洲や甚目寺もこの湿地帯の中にあった。ここは稲作に適していたが、大軍が駆け巡り会戦を繰り広げる土地ではなかった。それに比べ、周囲の大名の武田、今川、斉藤、浅井、朝倉、松平氏たちはみな乾いた大地を持っていた。その土地では騎馬軍団や兵卒が駆け巡り、布陣を張り、敵と対峙し、戦闘を交える戦国絵巻が展開されていた。その同じ時期、織田一族は、3代にわたり一族内部で血で血を洗う陰惨な闘争を繰り返していた。・・その中で生まれ育った信長は、大地を駆け巡り、布陣を張り、敵と対峙し、戦闘を交える会戦を経験していなかった。信長は戦国の戦いを知らない。戦国絵巻から疎外された武将として戦国の世に登場した。この信長が強いわけがない。弱くて当然であった。その弱い信長が、戦国最強の敵に次々と勝ってしまう。これが信長の謎である。
といった前振りから初めて、桶狭間や長篠の戦の意外な側面(桶狭間の戦いは「特攻の戦」、長篠の戦は「卑怯者の戦」ってな具合に結構手厳しい)から
平時の信長は全軍の将として、人格的にも武将としても見劣りする。ところが、絶対絶命の状況に陥ったり、勝ち目のない戦いを前にすると、信長はとたんに魅力的になる。誰も考えたことのない戦術や武器を思いつき、それを実行する。(中略)「信長は弱かったのか?強かったのか?」の問いの解は「信長は弱いから強かった」である。信長はやはり天才であった。弱者であること、逆境にいることを創造のバネにした天才であった。
というあたりは、信長の神格性を否定しつつも、別の形で持ち上げているあたりが興味深い。
そのほか、日本人がなぜ「小さいもの」を志向するか、や日本人の無原則性も気象からとするあたりは、ちょっと飛躍っぽいよな、と思いつつ、こうした歴史読み物は、眉間にシワを寄せて論じるより、ほほーっと作者の手の内に乗ったほうが間違いなく楽しめる。
ネタは各種満載。一つ一つレビューしていると、ネタバレが過ぎるので、ここらあたりで了としておこう。詳しくは本書でお愉しみを。
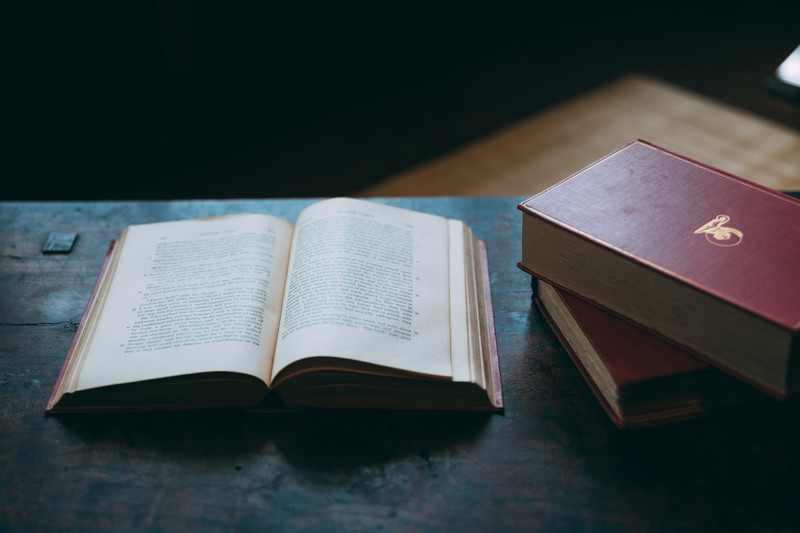

コメント