フランス国王からの委託を受けて、パリで死刑を宣告された囚人の処刑を執り行う一族「サンソン家」の一員で、ルイ16世やマリーアントワネット、ロベスピエールなどフランス革命期の多くの有名人の首を刎ねた伝説の「シャルル・アンリ・サンソン」と女性でありながらベルサイユの処刑人「プレヴォテ・ド・ロテル」となった妹「マリー・ジョセフ・サンソン」を中心に、フランス革命を裏面からとらえた歴史コミック・シリーズ「イノサン」の革命篇となる『坂本眞一「イノサン Rouge」(ヤングジャンプコミックス)』の第1弾と第2弾。
前シリーズ「イノサン」では、死刑執行に疑問をいだきながらも処刑を続けるうちに、ルイ16世という理解者を得、死刑囚に一番苦痛のない「ギロチン」の開発に前ざめたシャルルと、ベルサイユの処刑人であるとともに、アントワネットの信頼を得て警備隊長となったマリーのそれぞれの「フランス革命」が始まります。
【スポンサードリンク】
あらすじと注目ポイント
第1巻 シャルルは王家に忠実な処刑人、マリーは貴族殺しの処刑人へと袂を分かつ
第1巻の構成は
n°1 血塗れの純真
n°2 夢現の死刑執行
n°3 誇り高き一族
n°4 生命握る手
n°5 清濁の世界
n°6 静かなる運命
となっていて、冒頭では、処刑場に後の五代目となる「アンリ・サンソン」を連れてきて、彼にその様子をみせなが冷徹に刑を執行する四代目シャルル=アンリ・サンソンの姿が描かれます。前篇では、車裂きをする前に、首をこっそり締めて絶命させてやったり、死刑囚を苦しませない処刑が売り物だったのですが、子供ができ、「ムシュー・ド・パリ」として、サンソン一族をその肩に担う立場になった上に、妹マリーと決別した後のシャルルは国王の命令い忠実な、冷酷無比な処刑が売り物になっています。
一方、ベルサイユの処刑人「プレヴォテ・ド・ロテル」に復帰したマリーは、幼馴染であるカリブの農場主「アラン・ベルナール」を貴族たちに殺されたことから、「貴族鏖し」を心に秘めて職務にあたっています。
今回もアランを射殺しながら、ルイ15世の公妾「デュ・バリー夫人」に賄賂を贈って罪を免れた貴族ド・リュクセに罠をかけて、その犯罪を王太子の前で自白させ、処刑台に乗せています。
彼の処刑の後、「貴族が死んだ!!」と歓声をあげる死刑台を取り囲む民衆の姿はしばらく後の「フランス革命」の前触れのようですね。
中盤部分では、サンソン宗家の五代目となるアンリ・サンソンがだんだんと処刑人の職務に目覚めていく物語です。彼はサンソン家の病院セクションに入院してきた12歳の妊婦エレーヌ・ヴィルヌーブと知り合いになるのですが、彼女に死体の臭いがすると言われ、家業が嫌になってきています。
そんな折、妊婦の容態が急変し、母体も赤ん坊どちらの命も危なくなったため、シャルル・アンソンはこの当時、誰も試していなかった「ダチュラ」による全身麻酔をしての帝王切開を試みるのですが・・という展開です。
手術の成功を喜ぶアンリだったのですが、父たちが帝王切開で母子を助けた驚愕の理由を知ることとなるのですが、という展開です。
後半部分は、仮面舞踏会に出かけるマリー・アントワネットとアラン・ベルナールの形見の大ダイヤモンドをベルサイユ宮殿出入りの宝石商べーマーと宝石工バッサンジュに提供するマリー・サンソンが描かれます。マリーは、この首飾りを買えば、国王が破産しかねない、という話を小耳にはさんで絡んできた、という設定ですね。
フランス王家を揺るがし、フランス革命の遠因ともなった「首飾り事件」の発端ですね。
第2巻 初代「ムシュー・ド・パリ」は」いかにして誕生したか?
第2巻の構成は
n°7 初代サンソンの言葉
n°8 女神の罠
n°9 原罪の夜
n°10 その漢、呪われん
n°11 紅血の創世記
n°12 本当の「敵」
n°13 呪いの名は「愛」
となっていて、今巻の中心人物は代々、処刑人を務めることとなった「サンソン一族」の初代シャルル=サンソン・ド・ロンヴァルがいかにして処刑人になったかの話です。
初代サンソンはフランス陸軍の軍人をしていたのですが、死んだ兄の妻コロンブをさらって逃げる途中で雷にあって遭難し、とある家に救助されます。
その家の一人娘マルグリットに一目惚れしたサンソンは、彼女に夜這いをけけようとする仲間から彼女守り、マルグリッドに求愛するのですが、実は彼女は処刑人の娘で・・という展開です。
マルグリッドへの愛ゆえに、名門で軍人の一族を離れ、処刑人を継ぐことを選んだ初代サンソンの話は一応「美談」っぽいのですが、彼を虜にしたマルグリッドの目的は何だったのか、女の怖さが溢れ出てくる一代記となっていますね。
レビュアーの一言
第1巻の最後では、マリー・サンソンがアラン・ベルナールがインドのマハラジャから貰ったダイヤモンドを宝石商ベーマーに提供しているのですが、フランス王家と関係のあるインドのダイヤモンドといえば、ジャン・バティスト・タベルニエが、インドのムガール帝国で手に入れ、ルイ14世に献上した「ホープ・ダイヤモンド」が有名ですね。
タベルニエはこのダイヤモンドをインドの僧院の女神の像の目であったのを盗み出し、そのときに僧院の僧侶が呪いをかけた、という伝説が残っています。
このダイヤモンドはルイ14世によって67と1/8にカットされ。フランス王宮に所蔵されていたのが、1792年、フランス革命の起こった年に盗まれ、その後、所有者を転々とするのですが、持ち主のいずれも不幸に見舞われたという伝説がここで生まれています。
【スポンサードリンク】

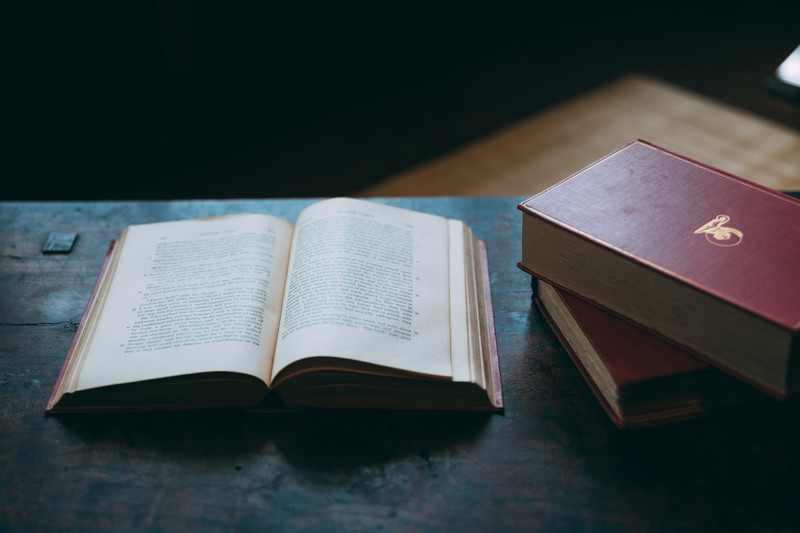



コメント