地震や台風と並んで、日本列島を襲う大きな自然災害の一つに「噴火」があります。鹿児島の桜島や長崎の普賢岳をはじめいまなお活発な火山活動をしている「火山」が日本各地にあるのですが、なかでも過去に大きな災害をもたらしてきたのが長野県と群馬県の間にある「浅間山」です。
その浅間山が大噴火を起こし、周辺地域を壊滅状態に陥れ、さらに噴出した火山ガスや噴煙で北半球に低温化と冷害をもたらした「天明の大噴火」の時代、村人の8割が犠牲になったある村を舞台に、残されたわずかな人々を中止に故郷の復興に挑んだ幕府の役人と村人の奮闘を描いたのが本書『赤神諒「火山に馳すー浅間大変秘抄」(角川書店)』です。
あらすじと注目ポイント
物語の構成は
序 木曽の暴れ川
第一章 なんかもん
第二章 咒原(のろいばら)
第三章 デーラン坊の涙
第四章 家族ごっこ
第五章 江戸のダイダラボッチ
第六章 形見
第七章 祈り
第八章 花畑
となっていて、物語は浅間山が大噴火をおこした天明三年の役30年前の宝暦三年、木曽川の大氾濫の災害対策にあたっている安生という幕府の役人の描写から始まります。この地では、昔から氾濫が相次ぎ、その防止のために薩摩藩がその財政負担に苦しみながら施工した「宝暦治水工事」が行われているのですが、その少し前あたりのことで、災害地を廃村として住んでいる百姓たちを追い出した対策が本編との対比を生み出していることとなります。
ここはあくまでも推測ですが、この時に現地に派遣されている「目付」が後の田沼意次のような気がしています。
で、本編のほうは、それから30年後の今の群馬県あたりの「鎌原村」という500人弱の村人が暮らす農村へと移ります。
本編冒頭では、小さな噴火をし、小石が降ったり地鳴りは続いているものの大事には至らないだろうといつもと変わらない日々の暮らしを営む人々の姿が描かれていきます。妻の連れ子の男の子「仙太」との折り合いが悪いのに悩みながら、暮らし向きの一発逆転を狙って「どぶろく」造りにいそしむ男「音五郎」、貧しい百姓の末っ子で、継母とその連れ子の兄姉にいつもいじめられている「すゑ」、村人皆から頼りにされ、浅間山の噴火からしばらく避難すべきだと村人を説く若き百姓代「一二三」と妻「玉菜」など、それぞれが明日も今日と同じ平穏な日々が続くだろうと思い込んでいるところへ、浅間山の大噴火が襲います。
浅間山の噴火は7月3日に発生し、その風向きと山の切れ具合の関係で噴煙と溶岩がまともに村とその田畑に向かい、避難所と考えていた高台にある寺や神社の敷地を呑みつくし、生き残った村人は前述したうちの一二三を除く3人を含む90人足らずという大惨事になります。
そして、壊滅に近い被害を受けた鎌原村を含む上州の各地は大きな被害を受けるのですが、この救援活動の目付として幕府から、数々の災害復旧で功績をあげてきた「根岸九郎左衛門」が派遣されるのですが、彼が見たのは肉親を失い、将来に希望を失なっている村人たちです。
壊滅状態にある村の状況に、上州の代官をしている田沼意次の子飼いの旗本・原田清右衛門ほかほとんどの幕臣たちが、鎌原村などの「廃村」を進めようとするのですが、根岸一人がそれに反対し、強引に村の再建計画を推し進めようとします。
根岸とともにその再建計画にあたったのが、災害死した百姓代・一二三の親友の「吉六」だったのですが、その彼も遅々として進まない村の再建と打ちのめされて動こうとしない村人たちに絶望し、避難所の柱に縄をかけて自死してしまいます。
多くの障害で、根岸の再建計画も頓挫するかと思われたのですが、吉六の死で、妻と母を失い、再掲計画に意固地に反対を続けていた「音五郎」が根岸に協力を申し出ます。
上州の方言で、気が強くて生意気な若者を意味する「なんかもん」の異名をもつ音五郎の行動は次第に周囲に村人たちを巻き込みはじめ・・と展開していきます。
とはいっても、ここで復興が順調に進んでいくというものではなく、巨額の復興資金が必要なため、途中で資金投入を中止して他の公共工事(印旛沼干拓)へ資金を振り替えようとする幕府の動きがあったり、復興のための公共工事費の中抜きによるぼろ儲けを狙って江戸の商人たちが強引に参入しようとしてきたり、いったんはまとまりかけてきた村人たちも次の噴火があるというデマで動揺し始めたり、と災害の「その後」につきものの出来事が起きてきます。
さて、この難事に、根岸と音五郎、そして音五郎と一緒に暮らし始めた仙太とすゑたちはどう立ち向かっていったのか、「鎌原村の奇蹟の災害復興」の詳細については原書のほうで。
レビュアーの一言
本作で印象的なのは、鎌原村の復興の中心的存在となる目付の根岸と百姓代の音五郎のほかに、音五郎の義理の息子「仙太」と水呑み百姓の娘で親と兄姉からイジメられながらも明るく育った「すゑ」ではないでしょうか。
仙太とすゑは村から小高いところにある観音堂に逃れて助かるのですが、今一歩のところで仙太の母親と祖母は土石流に呑み込まれて災害死してしまいます。この二人が昭和59年の発掘調査で階段下から発見された老年の女性を背負った中年の女性だった、という設定ですね。
浅間山の噴火で、鎌原村は6メートルも埋まってしまうことになるのですが、この正体は以前は火砕流だと思われていたのですが、発掘調査による出土品に焼け焦げた跡がないため、現在では土石流ではないかと考えられています。
これが鎌原村は浅間山の火口から12キロメートルは距離があるので、溶岩流であれば到達するまで3・4日かかるはずなのに、大噴火から数十分で村を襲い、村人が逃げる間もなく呑み込まれていった原因ではないか、と推定されていて、その原因は山腹でおきた水蒸気爆発ではないか、といわれています。
旧鎌原村(現在の嬬恋村鎌原地区)では、現在でもお彼岸のときには先祖を祀る祭礼が開かれ、その際に天明の噴火の様子をうたった「浅間山噴火大和讃」という声明が唱えられるそうです。
過去の大災害のことを風化させない先祖の知恵と言えるのではないでしょうか。
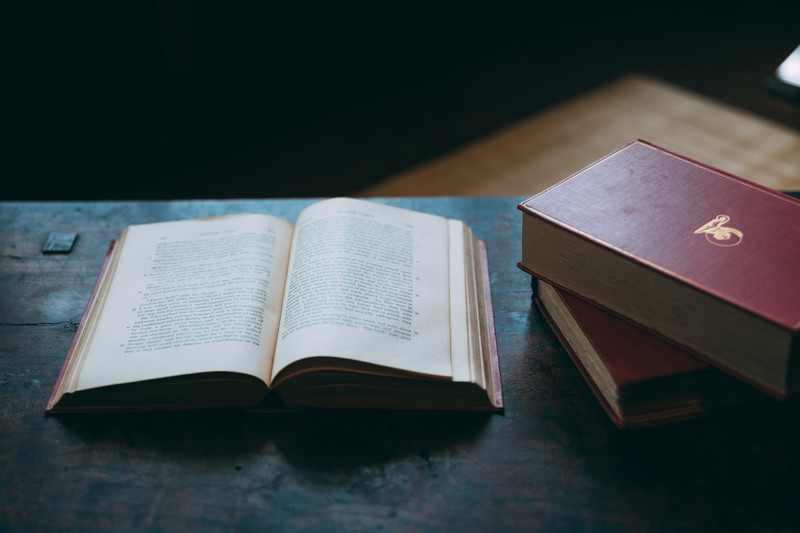


コメント