「リーダーシップ」という言葉を聞くと、高らかに「目標」を宣言し、矢継ぎ早にチームメンバーに指示している、カリスマ型のリーダーを思い浮かべる人が多いのではなかろうか。書店のビジネス書のところに行くと、そういうリーダーになるにはどうしたらいいのかといったものや、そういうリーダーを希求するもので溢れているといっても過言ではない。
そんな「リーダー像」に対して
トップダウンの命令をただこなすだけの「指示待ち人間」ばかりが増え、リーダーのアイディアが枯渇した途端、組織の成長は停滞する。 「優秀なリーダーを据えているはずなのに、業績が伸びないのはなぜなのか」
多くの経営者たちが壁に突き当たった、というのがこの 10 年で起きていたことではないだろうか
と疑問を投げかけ、新しい「リーダー論」を提案するのが本書『中竹竜二「リーダーシップからフォロワーシップへ ー カリスマリーダー不要の組織づくりとは」(CCCメディアハウス)』である。
【構成は】
第1章 組織論の見直し
ー組織論の定義と分類
第2章 リーダーのためのリーダーシップ論
ーリーダーに求められる資質とは
第3章 スタイルの確立
スタイルの必要性
スタイル確立の鉄則
VSSマネジメント
スタイル確立の罠
スタイルの強み
第4章 リーダーのためのフォロワーシップ論
ーフォロワーをいかに育てるか
第5章 フォロワーシップの実践
ーフィロワ−育成の中竹メソッド
第6章 フォロワーのためのフォロワーシップ論
ー個人と組織の関係性
第7章 フォロワーが考えるリーダーシップ論
ーフォロワーによる組織変革
終章 これからの時代のリーダーとは
優れたコーチの共通項
私自身の試行と成果、そしてこれから
となっていて、著者・中武竜二氏は、早稲田大学のラグビーチームの監督をしていた人で、名監督・清宮克幸氏の後をうけながら、前任とは違ったスタイルを確立し、学生たちの自主性を高めながら、チームの好成績を誘導した人物である。
【注目ポイント】
もともと、こうした風潮は、昨今の自動車会社のトップの件だけではなく、今まで時代の趨勢を読み、方向性を示してきた、として称賛されてきたリーダーたちが、在任の長さや時代がますます読めなくなったことによって、そのカリスマ性に疑問が出てきていることもあり、このため
事例研究、およびその体系化によって、従来型の属人的なカリスマ性に依存したリーダーシップが組織を必ずしも成長させないことが分かってきた。 いや、成長させないどころか、部下に上から目標を押しつけるだけのリーダーは、むしろ「ディミニッシャー(消耗させる人)」として否定されるようにまでなってき
た。
一方で、代わりに歓迎されているリーダー像は「マルチプライアー」、すなわち「増殖させる人」。自分だけが存在感を発揮するのではなく、部下一人ひとりが自ら成長し、活躍の場を広げる手助けをするリーダーシップが、組織の永続的成長に不可欠と考えられるようになった
と、今までの「リーダー論」が破綻をきたし始めてるのでは、ということをうすうす皆が思い始めたということであるのだろう。このため、一人のカリスマ・リーダーのすべてを託すよりも
通常、リーダーはその組織の中でリーダーにしかできないことがあればあるほど、リーダーとしての威厳を発揮し、存在感を出すことができるだろう。リーダーのためのリーダーシップの観点から言えば、それこそがリーダーたる所以と断言できる。 しかし、リーダーのためのフォロワーシップという観点から言えば、リーダーにしかできないことをゼロにすることが、リーダーの最大の役割
といった形で、リーダーが、メンバーのフォロワーとして機能したほうが、先の見えない中では、より安全でリスクが少ない。といった判断が、多くの人の中で主流になってきているということであろう。
もっとも、このフォロワー型のリーダーシップが「楽」かというと筆者の経験を読む限り、そうともいえなくて、カリスマ型リーダーと違って、頼りなく見えるせいか、選手の信頼が高まるまでには時間がかかったり、メンバーの脱退・組織崩壊の危機を迎えることがあったり、チーム・メンバーそれぞれに自主的な判断力をつけされるために「チーム・トーク」などの手法を取り入れるのだが、なかなかうまく機能しなかったり、と平坦な道のりではない。
ただ、
組織マネジメントにおいて、リーダー自身ができないことを無理矢理やろうとすれば、必ずといっていいほど、組織は崩壊する。自分の能力では到底できないリーダーの役割があったとすれば、いくつかの方法で対処しなければならない
といったように、リーダーが「万能」ではない場合や、ひょっとすると時代の変化が劇的すぎて、リーダーの能力では統御に苦労する場合など、フツーの人が「リーダー」を任される時に、「優れたリーダー」になろうと思えば、「フォロワーシップ」のテクニックはおさえておかないといけないように思えるのである。
【レビュアーから一言】
実は、フォロワー型のリーダーといっても、今までの「リーダー」とは全く別物なのではなく、そのリーダーシップの現れかたが、自分の存在を強く示すのではなく、他人の存在を強く示すことによって自分のリーダーとしての価値を、より強く示す形に変化しているに過ぎないという気がしてくる。
いわば、「独裁君主型」から「むらおさ型」へ、人々のリーダー嗜好が変化しているともいえて、案外に、フォロワーシプ型のリーダーは、カリスマ型に疲れた日本人の性向にマッチしているのかもしれない。
通常のリーダー論はあれこれ読んでみたが、いまいちしっくりいかないところがあるんだよな、という悩みがある管理者層は、一読しておいて損はないですよ。
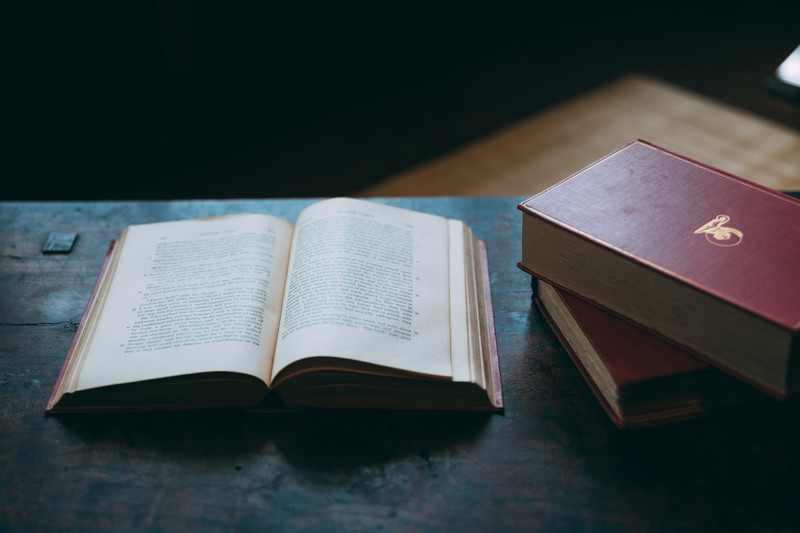


コメント