脳科学の視点から、いつも人間の行動に斬新な角度から光をあてている筆者が、今度は、日本のバブル経済の終焉期に著されたブラック・ユーモア漫画の傑作「笑ゥせぇるすまん」の主人公・喪黒福造の「騙し」のテクニックを題材に「人はなぜ騙されるのか」を解き明かしたのが本書『中野信子「悪の脳科学」(集英社新書)』です。

構成と注目ポイント
構成は
はじめにー簡単に騙される、人間という悲しい生き物
第一章 あるべくして不完全な人間の脳
<『笑ゥせぇるすまん』の世界観>
「♥ココロのスキマ・・お埋めします」という名刺
第二章 ラポールの形成
<喪黒福造の接近テクニック>
喪黒福造のコールド・リーディング
第三章 騙されるメカニズム
<ターゲットの心を操る喪黒福造>
人間の我慢の限界は、なにで決まるか
終章 騙されやすい脳と騙されにくい脳
詐欺師たちの常連客
となっていて、「なぜ私たちは騙されるのか」「騙す側はどうやってスキをつくのか」「騙すためのテクニック」という構成で、本書の特徴は、騙される側がどうやって騙されるのを防止するかではなく、どう騙したらいいのか、の視点で書かれているのがユニークなとこりです。
ただ、この視点はかなり有益なもののように思えて、よく私たちは、うかうかと騙されてしまった時に、「心の隙があった」せいだ、と思ってしまうのですが、筆者にいわせると
「ココロのスキマ」が存在することそのものが、「心」の要件なのだ。もし、こうした過激な言い方が許されるのなら、スキマがなければ、それは心ではないといってもいいだろう。
ということのようなので、人間というのは、「本来的に」騙される精神構造になっている、ということなんでありましょう。
このあたりは、第二章で、「喪黒福造」が騙される側の素性をいいあてたり(コールドリーディング)、信頼関係を構築するというテクニックを講じる時にも共通していて
コールド リーデイングといっても、しょせんはいくつかのカテゴリーに対象を当てはめ、最大公約数を求めるのと同じ要領で相手の身上をいい当てようとしているのだろう、ならば、相手が設定しているカテゴリーに当てはまらないような人物になればいい。・・・そう考える人が出てくるであろうが、この戦略には大きな落とし穴が潜んでいる。
たとえば人が、「Aであると悟られないように」と考えているとしよう。その時点で、自分がAであることを意識しすぎている。あるカテゴリーの持つ特徴あら逃れようとすればするほど、そのカテゴリーの特徴を不自然に避けるこよになり、そこに、また新たな特徴が現れてしまう。
であったり、
人間は誰でもひとりで生きることを避けるようにプログラムされていて、つねに仲間を探し、仲間と信頼関係を築きやすいようにできあがっているのである。
ということなので、どうやら、人間と言う「生物」は騙されまいと意識していても、知らず知らず「騙される」方向に進んでしまうようで、まさに「飛んで火に入る」状態のようですね。
そして、
ほとんどの人間は、命令されることを前提に作られている。これは、人間の臓器のなかで脳の消費する酸素が際立って多いということからも説明することができるだろう。人間が身体全体で消費する酸素量のおよそ四分の一を脳が使っている。
(中略)
人間の身体は、脳に対して本能的に「あまり働くな」と命じ、可能な限り脳も活動を効率的にすることで酸素の消費を抑えようとしているのだ。自分で考えようとせず、誰かからの命令に従おうとするのは、人間の本能、生理的機能の表れといえる。
といった、人間が他の動物より優位にたてる基礎となる「知性」をつかさどる「脳」がこうした「エネルギー食い」である以上、「騙されて」しまうのは避けようもないのかも、とちょっと暗澹とした気分になってきます。
ただ、こうした悲観的な結論だけ店て「終了」としないのが、筆者のエライところで、最終章で「騙される人」と「騙されにくい人」の分岐点となる「メタ認知能力」やその鍛え方についてとりあげてありますので、興味のわいた方は、原書のほうでご確認を。
レビュアーから一言
命令されることに抵抗がなくて、我慢強い、ていうのが「日本人」の特徴のようにいわれることがあるのですが、本書の第三章では
人間には「我慢の総量」があらかじめ決められていて、満員電車による通勤などでそのキャパシティを使ってしまっている場合は、ほんの少しのストレスが加えられるだけで、満杯のコップに水を一滴垂らしただけで流れるように忍耐の防波堤が決壊してしまう。
といったことも紹介されています。おざなりの説明や掛け声だけで、世間がどう言おうと自分の方針を進めようとしている「エライ方」がいるようでしたら、ダムが崩れると大被害をもたらすように、世間の防波堤が崩れないよう気を付けたほうがいいかもしれません。
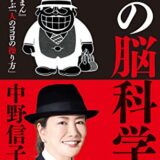
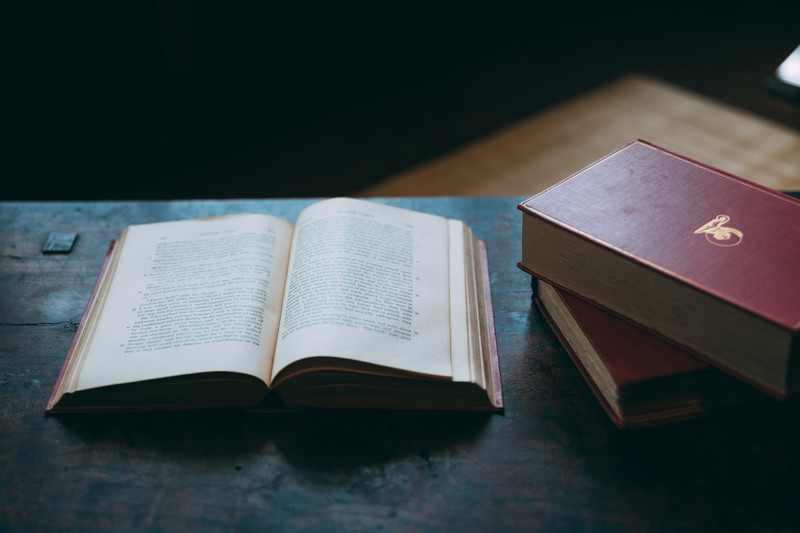

コメント