家族や親族の死というのは、たいてい突然やってくるものなので、当然、故人の葬式というものも準備がほとんどできていないのが一般的です。まあ、大筋のところは葬儀社さんに頼んでいれば大きな問題なく取り計らってくれるのですが、遺族が決めなければいけないこと、祭壇の生花であるとか、告別式の段取り、香典返しをどうするか、などなど数多くあるのですが、中でも故人の遺したものをひっくりかえしたりして大騒動となるのが「遺影写真」。そんな遺影を生前に撮影するのを専門にする写真館を舞台にしたミステリーが本書『芦沢央「雨利就活写真館」(小学館)』です。
本書の紹介文によると
『人生の最期に最愛の人へ最高の自分を贈るために』
巣鴨の路地裏に佇む遺影専門の雨利写真館には、今日も死に向き合う人々が訪れる。撮影にやって来る人々の生き様や遺された人の人生ドラマを若手注目ナンバー1新進気鋭のミステリー作家・芦沢央が見事な謎解きで紡ぎ出す。
人生の終焉を迎える時、人は、本当に大切な物が見えてくる。
ミステリー、なのに心温まる珠玉の4編。
ということで、遺影とその撮影の依頼者と写真館のスタッフによる謎解きと人間模様が描かれていきます。
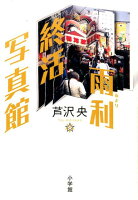
あらすじと注目ポイント
収録は
第1話 一つ目の遺言状
第2話 十二年目の家族写真
第3話 三つ目の遺品
第4話 二枚目の遺影
となっていて、冒頭では、この物語の主人公で語り手となる、有名美容院を寿退社したばかりの「黒子ハナ」という女性が巣鴨にある「遺影」専門の写真館「雨利終活写真館」を訪ねてくるところから始まります。
彼女の目的は、この写真館で遺影を撮影し、弁護士を紹介してもらった祖母が、遺産相続の遺言状に残した謎解きです。その遺言状は、赤い異国風の切手を貼った彼女の母宛ての封筒に入れられていたのですが、その内容が長男には家屋敷を、次女には貯金を遺すというもので、長女である彼女の母への遺産には一言も触れられていない、という内容です。
今までとりたてて不和でもなかった母はこの祖母の冷たい遺言に打ちひしがれてしまうのですが、ここにはクイズ好きでいたずら好きだった祖母の遺志が隠れているに違いない、遺影をとり終活カウンセリングをしてもらった、雨利写真館にやってきた、というわけです。
店の営業担当である夢子や、カウンセラー兼カメラマン助手の道頓堀からは何の手がかりも出てこず、途方にくれていたハナだったのですが、不愛想なカメラマン・雨利の「それじゃ届かないだろ」「こういうのに住所がないのは普通なのか?」「何で切手が貼ってある?」という発言に、祖母の出した最後の「クイズ」の内容と答えが閃いて・・という展開です。
第二話は、終活セミナーにやってきた高齢男性が、家族一緒で写真を撮影して、そこから遺影を切り出してくれという風変わりな依頼をもってきます。事情を聞くと、今は大学生の孫が幼い頃に描いたという配色がめちゃくちゃな画を見せられ、彼がその画を描いた半年後、孫の母親が団地のベランダから転落死したのですが、その時、孫は家に帰ってきていて、転落した母親に気付いていたにもかかわらず、救急車も近くの大人も呼ばなかった、という昔話を打ち明けられます。
それがきっかけで、父親は自分の息子にわだかまりをもちはじめ、現在ではほとんど没交渉になっているとのことで、老人は、この父子の間をとりもつために、遺影の写真を家族で撮影するというアイデアを思いついたようですね。
そして、その撮影の日、集まった家族の会話と、赤みがかった綺麗に見えない写真を遺影の候補に選んだ孫の選択から、ハナはこの事故に隠された孫の秘密に気付き・・という展開です。
このほか、二十五年前に撮影された、妊婦の女性と夫らしき男性の写真に隠されていた謎(三つ目の遺品)とか、愛人らしき人と奥さんと別々に遺影を撮影し、愛人へは奥さんと撮った写真を、奥さんへは愛人らしき人と撮った写真を送ろうとする男性の狙いを解きあかす話(二枚目の遺影)など、死を間際にしての人情話と謎解きが描かれています。
レビュアーの一言
アメリカあたりでは、エンバーミング(遺体保存の技術)が進歩しているのと、葬儀では柩をオープンにしておく風習や土葬の習慣がまだ残っていることなどから「遺影」という習慣は一般的ではないようで、「遺影」の風習は日本で独自進化を遂げたもののようですね。
もともとは江戸中期から明治後期まで行われていた「死に絵」という役者などの有名人が亡くなった時に、冥福を祈るために描かれた似顔絵の浮世絵が起源とも言われているのですが、昭和初期に大阪の「公益社」という葬儀社が業界初の葬儀カタログをつくり、高額な葬儀セットには「写真撮影」を組み込んだのが、一般化するきっかけになったとも言われています。
写真もデジタル化され、デジタル遺産として遺族が簡単にアクセスできなりつつある今日、生前に、自分で遺影を指定しておくというのはこれからの終活のマナーになるのかもしれません。
【スポンサードリンク】


コメント